
〇☓クイズは、小学生(子ども)でも答えやすくて家族やお友達まで皆で一緒に楽むことができるクイズ問題です。お正月休みは子ども達と一緒にお正月にちなんだ〇☓クイズで盛り上がりませんか?
そこで今回は、大人も子どもも一緒に盛り上がる【お正月にちなんだ〇☓クイズ】を20問ピックアップします。
目次
- 1 〇☓クイズ。お正月に盛り上がる問題【20問】
- 1.1 第1問
- 1.2 第2問
- 1.3 第3問
- 1.4 第4問
- 1.5 第5問
- 1.6 第6問
- 1.7 第7問
- 1.8 第8問
- 1.9 第9問
- 1.10 第10問
- 1.11 第11問
- 1.12 第12問
- 1.13 第13問
- 1.14 第14問
- 1.15 第15問
- 1.16 第16問
- 1.17 第17問
- 1.18 第18問
- 1.19 第19問
- 1.20 第20問
- 1.21 第1問の答え
- 1.22 第2問の答え
- 1.23 第3問の答え
- 1.24 第4問の答え
- 1.25 第5問の答え
- 1.26 第6問の答え
- 1.27 第7問の答え
- 1.28 第8問の答え
- 1.29 第9問の答え
- 1.30 第10問の答え
- 1.31 第11問の答え
- 1.32 第12問の答え
- 1.33 第13問の答え
- 1.34 第14問の答え
- 1.35 第15問の答え
- 1.36 第16問の答え
- 1.37 第17問の答え
- 1.38 第18問の答え
- 1.39 第19問の答え
- 1.40 第20問の答え
〇☓クイズ。お正月に盛り上がる問題【20問】

第1問
● 『元日(がんじつ)』と『元旦(がんたん)』は同じ意味である。
第2問
● 1月1日のことを『元日(がんたん)』、1月3日までのことを『三が日(さんがにち)』、1月7日までを『松の内(まつのうち)』と言われている。
第3問
● お正月になるともらえる「お年玉」。昔はお年玉として「おてだま」をもらっていた。
第4問
● お年玉をいれるお年玉袋のことを、「ポチ袋(ぽちぶくろ)」といいますが、「これっぽっち」という意味がある。
第5問
● 1月2日のお正月に『おめでたい言葉』を紙に書くことを『えんぎぞめ』と言う。
第6問
● 1月2日の夜にみる夢を『初夢』と言いますが、『初夢(はつゆめ)』に出てくると縁起が良いと言われるのは、『おじぞうさん』です。
第7問
● 買ったときに片方の目を書いて、願い事がかなった時にもう一つの目を書くお正月の飾り物は、『だるま』です。
第8問
● 1月2日の夜の『初夢』をみるときに、枕の下におくと良いと言われているものは、『一万円札』である。
第9問
● 板と羽を使って遊ぶあそびを『けんだま』と言い、お正月の遊びとして知られている。
第10問
● お正月のおわりにお正月のかざりなどを焼く『どんどやき』の名前の由来は、どんどん焼くからである。
第11問
● お正月にかざっている「かがみもち」が二つに重ねるようになった理由は、縁起の良いだるまをイメージしているからである。
第12問
● 「かがみもち」の上にのせられている橙(だいだい)は、「だいだいお金持ちになるように」という意味でのせられている。
第13問
● お正月にふさわしい魚として、鯛(たい)がだされている理由は、「めでタイ」からである。
第14問
● お正月に食べるおせち料理は、神様のおそなえものとしてだされた料理です。
第15問
● 1月15日の小正月(こしょうがつ)の行事である『どんどやき』に焼いて食べられているのは『やきとり』である。
第16問
● お正月に食べられる『おせち料理』に入っているものクイズ①「かずのこ」は、“にしん”という魚の卵である。
第17問
● お正月に食べられる『おせち料理』に入っているものクイズ②「こんぶまき」をおせち料理に入れる理由は、「しあわせをはこんぶ」という意味があるからである。
第18問
● お正月に食べられる『おせち料理』に入っているものクイズ③「まめにはたらく」という意味でおせち料理に入れられているものは、「えだまめ」である。
第19問
● お正月に食べられる『おせち料理』に入っているものクイズ④「腰が曲がるまで長生きできますように」という願いから、おせち料理に入れられているのは、「えび」である。
第20問
● 1月7日に食べると病気にならないと言われているのは、「うめぼしがゆ」である。
第1問の答え

A=×
『元日(がんじつ)』とは、1年の最初の日のことで、1月1日全体のことをいいます。一方『元旦(がんたん)』とは、1月1日の朝のことを指している為、同じ意味ではありません。
第2問の答え

A=〇
年神さまを迎えるために、家の前に飾る「門松」を飾っている期間、つまり、神様がいる期間のことを「松の内」と呼ばれています。
一般に7日までを示しますが、10日の地域もあれば、15日までという地域もあり、地域によって考え方がさまざまです。
第3問の答え

A=〇
昔のお年玉は、「おもち」でした。「年のはじめに神様から魂をわけてもらう」という理由から、おもちが配られていました。
第4問の答え

A=〇
「これっぽっちですが…」という意味から、ポチ袋(ほちぶくろ)という名前がつけられました。
第5問の答え

A=×
お正月に『おめでたい言葉』でふさわしい文字を紙に書くことを『かきぞめ』と言います。
第6問の答え

A=×
『いちふじ・にたか・さんなすび』と言われており、ふじさん・たか・なすびが『初夢』に出てくると縁起が良いと言われています。
第7問の答え

A=〇
まず両方の目がまっしろの『だるま』を買って、願いをこめながら片目を黒くぬります。そして、願いがかなったらもう一つの目をぬります。
第8問の答え

A=×
『初夢』をみるときに、枕の下におくと良いと言われているのは、「七福神(しちふくじん)」と言う7人の神様の絵です。良い夢がみれると言われています。
第9問の答え

A=×
羽子板(はごいた)と羽をうお正月の遊びを『はねつき』と言います。江戸時代には、女の子のいる家庭に縁起が良い贈り物として年の暮れにおくられるようになりました。
第10問の答え

A=〇
『どんどやき』とは小正月(こしょうがつ=1月15日)の行事で、正月の松飾り(まつかざり)・注連縄(しめなわ)・書き初め(かきぞめ)などを家々から持ち寄り、に1ヵ所につみ上げて燃やすという、日本全国に伝わるお正月の火祭り行事です。
第11問の答え

A=×
昔はおもちを『サンドイッチ』のようにおかずをはさんで持ち歩いていたことから「かがみもち」を二つ重ねるようになりました。
第12問の答え
A=×
橙(だいだい)のだいだいをかけて、「だいだい家が続いていく」という意味でのせられています。今では橙(だいだい)ではなく安く手に入るという理由からみかんが代わりにのせられている場合が多いです。
第13問の答え
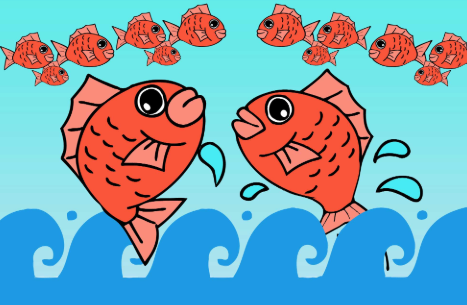
A=〇
昔から赤色は、お祝いの色とされていて、赤い魚の鯛(たい)のは、「めでタイ」ということでお正月にだされています。
第14問の答え

A=〇
昔おせち料理は、神様におそなえするものとして「せっく」と呼ばれていましたが、今では「おせち」と呼ばれるようになっています。
第15問の答え
A=×
『どんどやき』で、お正月に飾ったものをどんどん焼いた後は、棒につけたおもちを焼いて食べられています。どんどやきの火にあたったり、焼い団子もちを食べれば、その1年間健康でいられるなどの言い伝えがあるのです。
第16問の答え
A=〇
にしんは、別名で「かど」とも呼ばれ、「かどの子」がなまって、「数の子」と呼ばれるようになりました。にしんの卵は5万~10万個もつまっているため、子孫繁栄(しそんはんえい)の願いをこめておせち料理に入れられるようになりました。
第17問の答え
A=×
「こんぶまき」のこんぶは、「よろこんぶ」という意味をかけられているため、おせち料理に入れられています。
第18問の答え
A=×
「まめにはたらく」という意味でおせち料理に入れられているのは、「くろまめ」です。一生懸命(いっしょうけんめい)働いて、元気に暮らせるように、という意味がこめられています。
第19問の答え
A=〇
えびの姿のように、腰が曲がるまで長生きできますようにという願いから、おせち料理に入れられています。
第20問の答え

A=×
1月7日に食べると病気にならないと言われているのは、「七草粥(ななくさがゆ)」です。お正月に食べすぎて、弱ったお腹にとてもいい7種類の草(セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロ)が入ったおかゆのことを言います。
関連記事はこちら










